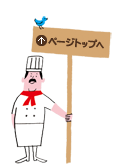「いもはお前に限る」といわれて

明治四十二年、十三歳の時、学帽をかぶり、ほうば、かすりの着物姿でベルモントホテルに通ったのが修業の始まり。
まだ薄暗い町の中を、眠い目をこすりながら出勤した。六時までにストーブをおこし、宿泊客の朝食のためにオートミール、卵、ベーコン、ハムなどを用意して先輩の出てくるのを待っていなければならない。誰でもが味わう下働きの辛い時代だ。
しかしこの下働きの時代にも楽しい思い出がある。それは毎日毎日三十キロからのいもの皮むきをさせられ、手に大きなマメを作ってがんばった。これが上達して廃棄が一割以内に留まり、いもの皮むきでは先輩にも誰にも負けない自信がつき「いもはお前に限る」といわれた時だ。
今から考えて見れば、単純でつまらないことだが、若い私には仕事に対する自信と喜びを与えてくれた。
ベルモントホテルで一応の仕事を覚えた後は、グランドホテル、ロイヤルホテル、オリエンタルホテルに首をつっこんだ。昔は多くの職場を変わることによって新しい技術を身につけ、メニューをたくさん知ることが、良い技術者になる修業の一つとされていた。
その後フランス人のコットー氏が経営する店に二番コックとして入ったのが十七歳。年令の割に早く二番コックにしてもらい、人の上にたたされ、多くの仕事を与えられて、勉強のチャンスをつかんだ。二番コック時代は長く、その大部分は外人のチーフのもとで働いた。おかげで、本場の料理を覚えることができ、語学力もつき、英仏語のメニューも書けるようになった。また昼のあき時間には、十三歳までに受けた教育だけではいろいろの面にマイナスが多いと思い勉強に励んだ。
フランスホテル、鎌倉海浜ホテル、テントホテルなどを経た後、昭和三年に横浜ニューグランドホテルに入った。
ここで私はスイスから来たワイル氏のもとで働き、それまで洋食といえば、定食だけだったものを、味本位に考えられたアラカルト料理を学んだ。このアラカルト料理の誕生によりグリルルームもでき、料理界も幅広くなってきた。
昭和の戦争により、この料理界も一時マヒ状態になって、暗いいやな時代を味わった。
戦後は二十六年からアラスカや三和のチーフを勤め三十五からキャッスルのチーフになった。
一方、国際料理技術協会や司厨士協会の相談役を勤め技術者の指導にもあたっている。
相談役をしたり若い者と一緒に働いていて感ずることは、どうもこの頃の若い人達は忍耐がたりないようだ。現在は学校を出てから修業に入ると、独身時代の身軽な時が短い。この短い身軽な時期が一番大切な修業時代でありながら、誘惑に負けて遊びに夢中になって、いいかげんな仕事しかしない者が多く、将来が思いやられる。料理の道で大切な語学もこの時期に学び、英仏二ヵ国語はマスターしておかなければ、良い技術者になり得ないだろう。勉強するための学校もできているし、よい参考書がたくさんそろっている。信用ある書物によって、自分自身で学び取ることだ。日本における西洋料理の水準は世界的にも高く評価されている。材料の良いこと、味のこまやかなことなど、けっして本場フランスにひけをとらない料理ができるのである。
この技術をますます高度のものにしていくには、若いあなた達自身の強い研究心とたゆまぬ努力による以外達成されないと思う。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)