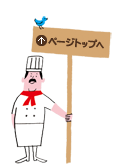見ただけで素材の主張が伝わる

存在感のある料理が理想です
私はこれまで、同じ料理を何年もくり返しつくり続けるということをあえて避けてきました。ルセットを書き留めておくこともしないので、一度メニューからはずしたものはもうそれっきり。それに代わる料理は毎日あらためて考えるというように、シーズンごと、あるいは年ごとに、常に新しい料理をつくることだけを考えてきました。
調理場のスタッフも、同じことのくり返しでは仕事が単調になりがちで、感動も少ないし、つい気がゆるんでしまうこともあると思う。サービス陣にしても、最初は気合いを込めて「さあ、どうぞ」とお出ししていたのが、だんだん素っ気なくなってしまったり……。新しい料理をつくり続けていれば、私もスタッフも、いつも緊張感があり、一皿一皿新鮮な気持ちで取り組むことができます。それに何より、お客さまが喜んでくださる。そんなこともあり、これとこれを組み合わせたらどうなるだろう、この調理法をこう変えてみたらどうなるだろう、といつも変化を求めてきました。
ただ、新しいことばかり求め続けていると、素材の組み合せ方に無理が出たり、こじつけ的なところが出たりするものです。つくった当初は満足していたものでも、しばらく時間をおいてみると手直ししたいところがいろいろ見えてくるんですね。たとえば、味のバランスさえ壊れなければ、お皿の中の色合いが寂しいからと、ついトマトを添えたりすることがあるでしょう。でもその料理のコンセプトからすればなくてもいい。むしろ抜いたほうが、ずっとおいしさが際立ってくるということがわかってきたのです。つまり、いかにそぎ落として、しかも、見ただけでおいしさが伝わってくる料理にするか。
今回ご紹介したアユの料理(長良川天然鮎の燻製、キャヴィア添え、タデ風味)は、その意味でまったく無駄がない料理だと自負しているものです。見た目は華やかとはいえませんが、構成要素の一つを除いただけでも料理としては成り立たない。どの素材も絶対に欠かすことのできないものです。(中略)
また、最近しみじみ思うのは、たとえば豚肉をローストしただけのもの、あるいはサバをこんがリグリエしたものなど、地味な素材でも、それを的確に調理した時のおいしさはやはり捨てがたいものだということです。素朴なものでも、それ自身に充分に力があるなら、その強みを一皿向に出してもよいのではないか。飾りの似合わぬものならいっそ飾らず、おいしさを引き出したい。そういった料理を自分のレパートリーとして増やしていけたらと思います。(中略)
素材でいえば、私の場合、冷凍食品でも質がよければ好んで使います。アワビでもオーストラリアのものなら半額で提供できるので、国産にこだわらずに輸入品も積極的に。それによって、お客さまがアワビというおいしいものに接することができればいいと思うんです。オマールにしても、ブルターニュ産とカナダ産では違いがありますが、それは質の良否の問題ではなく、異なる海で育った別個の素材であり、それぞれの持ち味があるものだと思います。
味はいいけど洗練されていないぶん、学ぶ側は勉強になりました
――森本氏は、一九八九年から三年間をフランスで過ごした。ブルゴーニュ、バスク、ブルターニュ、シャンパーニュなどもっぱら地方を巡る修業で、一軒につき半年間、計六つのレストランを回った。シェフの個性も料理への取り組み方もさまざまで、シェフとしてのあり方やフランス料理の組立てを考えるうえで、それぞれの体験がとても勉強になったという。
バスクのレストランは、「オーベルジュ・ド・ラ・ガループ」という店で、九七年に二ツ星に昇格しましたが、その知らせを聞いた時、やはりと納得するものがありました。バスク地方のとてもクラシックな伝統料理をつくっていましたから、けっこう粗削りなんですが、きっと二ツ星を狙える店だろうと思っていました。この店の料理は味はいいのだけれど、洗練さに欠けていたんですね。でも、洗練されていないぶん、学ぶ側としてはとても勉強になりました。三ツ星の料理は完成された料理ですから、まったく手の加えようがないですよね。そっくりそのままつくるしかない。その点、発展途上の料理はいかに手を加えるか、つくる側に考える余地が残されています。頭を使わなければならないんです。
また、「ミッシェル・ゲラール」のすぐそばにある「パン・ラドゥール・エ・ファンテジー」という店は、料理がすごく攻撃的で、はっとさせられることもたびたびでした。カキ油やゴマ油を使ったり、ひき肉やクワイなどを炒めた料理を仕上げにコーンスターチでつないだりと、一歩間違えたら中国料理じゃないかと思えるものを、すごいだろうといって教えてくれるんです。でもそのひき肉は鳩や鴨の肉。中国料理の技法を生かしながら、でき上がったものはきちんとフランス料理になっていたのはさすがでした。
フランス人の料理に対する創作意欲は旺盛で、ずいぶん刺激を受けたものです。私自身も、旧来のスタイルにとらわれず、自分なりのしっかりとしたメッセージを持って素材の存在感を感じさせる料理を提供していきたいと思います。
■森本秀和(もりもと・ひでかず)
1963年、和歌山県生まれ。大阪あべの辻調理師専門学校卒業後、同校に3年間勤務する。その後、「リオン・ドール」(大阪・堂島)を経て89年に渡仏。「ラ・ロティスリー・デュ・シャンベルタン」「ローベルガード」「オーベルジュ・ブルトンヌ」など地方の6軒のレストランで修業し、91年に帰国。「ステラ・マリス」(神奈川・小田原)を経て、94年より「レストラン馮」の料理長を務める。2002年、「サリュー」(東京・恵比寿)をオープン。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)