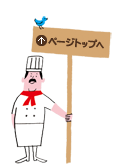日本料理は和音のようなもの

人の和というものの上によい仕事が生れる
自分のこれから進む道をそろそろ真剣に考え、決める必要にせまられる年になって、思い切って私は学業を捨てて、料理の見習いに出てみる気持になった。
当時は満州事変、支那事変とさわがしい世の中であり、若い私も、歴代の料理屋の長男として何かこうしてはいられないという私なりの不安な状態が続いたからである。今にこのさわがしい世の中の余波が必ず日本に、京都にやってくるにちがいない。そして大きくこの料理の世界にも影響を与えるにちがいないと考えた私は、何か嵐のくる前の静けさ、平隠さを感じる中に、今のうちにしっかりした力を身につけなければと思ったのである。
そしてまた、歴史の上にどっかりと腰をおろしてしまっている京料理というものが、このままでは進歩することもなく、今に時代に取残されていくかもしれない。こういつたことを考えて、学業に進むより、やはり料理の世界に入ってゆくことが、私に与えられた一つの義務であるような気がした。こうして私は東京に修業に出ることになった。
修業に入る店を選ぶ時、私はのれんよりまず自分が入っていけるムードを持つ店かどうかをみた上で決めることにした。私は仕事の上でのつらい事に耐えていく強さは持っているつもりであるが、しかし実際に自分がどうしてもとけこめない雰囲気を持つ店であった場合、毎日の生活の中で不満を持って仕事をすることになれば、これは自分にとっても大きなマイナスになると思ったからである。
のれんのある大きな店ということも修業する店を選ぶ場合、必要なことの一つである。しかし私はそういうところに入ってしまえば、末端のものしか得られないかもしれない。それよりも小さくてもいい、尊敬する主人や料理長の目が、見習いの中の手の先にまでとどくような店を選ばなければいけないと思った。
私の入った店は、料理人たちで作る野球チームがあったり、皆で楽器をいじったり、非常に明るい雰囲気を持つ店だった。そこで私は人の和というものの上によい仕事が生れ、よい料理が作られるものだということを学んだわけである。現在の私の店でも皆で野球チームを作っているが、チームにも加わらず、皆の中になかなかとけこめないでいる人というのは、仕事の上でも何か欠けることがあったり、店をやめていくようなこともあるようだ。
見習い時代の修行で「出合い物を知る力」を身につけた
見習いに出る人間の型には、大体三通りのタイプがある。一つはどこどこで修業した経験があるという肩書きを得るため、二は他人のめしを一度は食っておいたほうがいいだろう、修業に出ておいたほうがいいだろうとすすめられて出かける型、そして三はとにかく修業に出て何が何でもいい技術を身につけるまではという型。これらは実際に修業するきっかけも、目的も異ってくるのだから、そこにおのずと仕事に向かう気がまえも違ってくるわけである。
いずれも見習い時代の苦労はきびしく、つらいことが多いものであるが、その苦労を買って出るくらいのものでなければいけない。人のいやがる仕事や、人目につかない仕事をまず進んでやってみる。私の知っている人は、主人の食べる昼食を、毎日そこにある材料を使って作ることをすすんでやってみた。毎日のことだから、同じような材料をもって献立を考え、口のうるさい主人のために食事を作るという仕事は誰もが敬遠するものである。しかし、その人は、毎日それを続けることによって、料理の工夫、材料を無駄なく使う、変化に富んだ料理を作るなど、数々の力がうんとついた。
見習い時代の修業の方法についてはいろいろのものがあるが、私のやってきたのは、その日その日冷蔵庫をあけて、その中に入っている材料でもって、毎日料理献立を立ててみる、そして当時、私の師匠であった池田先生にみてもらうことだった。こうしてある材料から工夫すること、また出合い物を知る力を身につけることができたのである。
物そのものの味が料理の中に生きている日本料理は、結局、物と物との組合わせによって、おいしくもまずくもなるものである。いわゆる音楽でいう和音と同じで、美しい音と音の重なりというようなものが日本料理には大きな問題となるわけである。
現在は時間に合わせて仕事をする時代になったが、むかしはちがった。時間というものには束縛されず、時間を無視して人間のほうが仕事に使われていたのである。煮物が出来上がるのを待つ気持というものも昔と今とではちがう。今のように碁やしょうぎをさして待つのではなく、じっと鍋の横に立って煮える音を聞きながら待っていたものである。
今の若い人たちに何もかも昔のようにしろというのではない。ただ昔の人間が仕事に向かう時の、きびしい態度を少しでも知ってほしいのである。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)