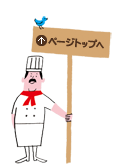料理人感覚で自分の味をつくり続けたい

1992年7月、杉野英実氏は、自分の名前をつけた店(パチシエ イデミ スギノ〈神戸・北野〉・現移転)をオープンした。はじめての自分の店だ。15~18種類あるこの店の生菓子には、いわゆる定番やどこにでもあるようなケーキは、ひとつもない。独創的なケーキばかりが並ぶ。スーボワ、アンブロワジー、パレノワ…。商品名も、フランス語がよほど分からぬ限り、「いったい何のこと?」という感じ。どれも繊細で美しいが、見慣れぬ菓子ばかりだ。(中略)
構成は複雑なものが多いが、どれもムダな要素はほとんどなく、すべて味や食感に生かされている。「バランスが優れている」のが特徴といえる。また、ごく一部を除き、季節によって品揃えが変わる。杉野氏の頭の中には、常に次の新しい菓子のことがある。
どうしてこういう菓子をつくるようになったのか。
「僕は、料理人の下でケーキをつくることが長かったんですよ。料理人的な発想が身に染みついていることが大きいと思いますね」
と杉野氏はいう。レシピ中心の菓子職人に対して、料理人は市場に行って素材を選び、そこから料理を決めていく。素材に合わせて料理法を「アレンジ」していくところが違う。まず杉野氏の足跡を追う。
菓子の世界に目覚めたのは、中学2年生の時だった。母が働く名古屋のホテルオークラを訪ねていった時、当時、同ホテルのシェフ・パティシエだったアンドレ・ルコント氏がつくる誕生ケーキを母から贈られた。そのケーキのおいしかったこと。また細工菓子にも目が吸い寄せられた。きれいだなぁ、と杉野氏は少年ながらにそう感じる。
「自分も、こんな菓子がつくれたら…」
高校卒業後の73年、東京ホテルオークラのベーカー部に入った時、すでにルコント氏は六本木で独立。が、ホテルという安定した職場の方がいいと周囲に勧められるまま、少年だった杉野氏は就職する。
「菓子職人の師匠らしき人はいなかった」と杉野氏が言うように、他のパティシエの中で働きつつも、上司は料理のシェフという構図。23才でパティシエの中で一番上に位置するようになった杉野氏は、料理長からの料理に合わせてこういうデザートや菓子をつくってくれという要望に合わせて、自由に菓子をつくることができた。そんな中、「素材が変われば、レシピや味を調整しないといけない」ことを、かたわらで学んでいく。この間、専門書をむさぼり読むようにして試作、失敗をくり返す中で菓子の技術を補強していった。
「料理長が好きにつくらせてくれたんですよ。仕事の後に残って、自分の勉強にと飴細工とかやっていても、何も言われなかった」
オークラで6年間、菓子のセクションをいろいろまわったが、本場の技術をもっと覚えたいと、この頃から杉野氏は渡仏を意識しはじめる。
フランスに行く前のできごとである。フランス語学校に通っていた当時、同級生だったデザイナーの卵に、杉野氏はこう言われる。
「オークラは素晴らしいホテルだというのは分かるけど、いったいあなたはどんなお菓子ができるの?」
常にオークラの話を自慢気に話していた杉野氏への痛烈なひと言。ショックを覚えた。この時から、「いつか、自分の名前でお客を引っ張ることができる菓子屋になりたい」と、杉野氏は思いはじめる。
「ジャン・ミエ」の深みのある菓子の味わいと、「ペルティエ」の繊細な菓子の美しさを吸収したかった
そして、79年、渡仏。25歳の時である。
杉野氏は、まずはアルザスのストラスブルグに行き、半年ほどホテルやレストランで働く。まずここで、カルチャーショックを味わう。
「しかられたんですよ。日本の製菓の基礎とまったく違っていた」
たとえば、日本ではきめ細かく柔らかいスポンジがいいとされたが違った。向こうではきめが粗いがシロップを打ち、生地自体が味わい深い。バヴァロアでも、日本では生クリームを6分立てにして加えるが、「とんでもない、めいっぱい立てろ。でないと重くなってしまう」と怒られる。「自分にもちょっとはできるんだぞ」というおごりから、日本のやり方に固執していたが、ここで素直に学ぶ大切さを知る。この時から、杉野氏は急速に、その地その店の技術やよさを吸収していくことになる。
その後、スイスのジュネーヴ近くの町、コペにあるレストラン、「ホテル・デュラック」に入る。もとオークラにいた菓子職人、ボニセリ氏が杉野氏を呼び寄せてくれたのだ。ここで父親ほどに歳が離れたボニセリ氏から、杉野氏は焼き菓子など、クラシックな菓子を学ぶ。そして半年後、ジュネーヴのレストラン、「ラ・ペルル・デュ・ラック」に移る。
渡欧以来、杉野氏は休みごとに毎週、パリに通っては菓子を食べ歩いていた。そんな中で吸収したかったのは、「ジャン・ミエ」の深みのある菓子の味わいと、「ペルティエ」の繊細な菓子の美しさだった。ジャン・ミエには半年いた。が、スイス時代から足を運んでいたにもかかわらず、ペルティエでは、当時のオーナー、ルシアン・ペルティエ氏に、「おまえに用はない」と追い返され続けた。ついにOKのサインが出、コック服に着替え、意気ようようと厨房に足を踏み入れたとたん、紹介者があって別の日本人が入ったからおまえはいらないと言われてしまう。連絡の行き違いがあったのだ。2~3日落ち込むほど、ショックだった。が、日本人の知合いにあきらめるなと言われ、とりあえず、今度はこれもきれいでおいしい菓子を出す「モデュイ」の門をたたく。毎日通っても断られ続けたが、せめて厨房を見せてくれと入ったところにシェフのドミニック・ルブルグ氏がいた。ダロワイヨにいた日本人パティシエ、熊坂孝明氏を尊敬する新日派のルブルグ氏のおかげで、彼の助手として働くことが許された。
半年いたモデュイでは、チョコレート、アイスクリーム、アントルメ(デザート菓子)などを学ぶ。この頃、母子家庭で育った杉野氏は体の弱い母が気がかりになっていた。どうしても帰国する前にペルティエで働きたい。そんな思いを知り、たまたまペルティエ氏の親友だったオーナーのピエール・モデュイ氏に取り持ってもらい、どうにか念願のペルティエ入りが実現した。ペルティエ氏自身に1年半いることが条件だと言われ、杉野氏は、「ウィ、ムッシュ!」と即答した。
しかし、杉野氏は4ヵ月ほどで退職し、帰国してしまう。母のことだけでなく、金が底をついたこともあった。日曜は朝3時の出勤。薄給では、タクシーで来いと言われても、続かない。歩いて40~50分の距離を通ったこともあった。早々に帰国する杉野氏にペルティエ氏は激怒したが、なぜか最後には高いシャンパンを開けてくれ、メニューに寄せ書きしたものさえ杉野氏に渡す。そして帰りの飛行機代は、モデュイ氏が出してくれたという。
薄給ではあったが、フランス人は門戸をいつも開放してくれていたことに感謝している、と杉野氏は懐かしそうに振り返る。それにしても、自分が吸収したいものについてはとことんあきらめなかった図太さ。それが、杉野氏のいまを支えている。
そこにある材料を生かして機転をきかす、そんな菓子が意外と売れるんです
杉野氏が渡欧して、もっとも影響を受けたことは何だったのだろうか。
「やはり、ペルティエの影響が強かったですね。常に怒っていて、満足しない人だった。いつも、ここがダメだから、じゃあこうやってみようとか、現状に甘んじない」
菓子の美しさもさることながら、ペルティエ氏の姿勢に、得ることが多かった。杉野氏は思い出したように、目を輝かせて言う。
「フランス人ってね、宗教上のこともあってか食べものを捨てないんです。だからクロワッサンが余るとシロップに浸してアーモンドクリームを挟み、上にアーモンドスライスをのせて焼いて『クロワッサン・ダマンド』に仕立てたりする。スポンジの切れ端も何か別の菓子に仕立ててしまう。そういうところにアイデアを感じるんです」
そんな菓子が意外に売れる。そこにある素材を生かして機転をきかすところにこそ、杉野氏は着目するのだ。そして、こうも言う。
「フランスのお菓子屋では、聞けば、なぜそういうつくり方をするかをきちんと教えてくれました。無名の店であってもそれぞれポリシーを持っていて、自分の菓子はどうで、だからこうつくるという考え方を、どんな形にせよ言ってくれるわけです」
固定観念ではなくて、自分の頭と舌で、味と技術の関係を確かめながら、杉野氏は菓子の技術を獲得していった。それと同時に、菓子屋にはポリシーが必要だということも、痛切に感じるようになる。
82年の帰国後、名古屋の「ポン・デザール」と、東京・代官山の「ピエールドオル」で相次いでシェフを4年ずつ務めた後、独立する。この2店でも、比較的自由に菓子をつくらせてもらえた。が、いまつくっている菓子とは違うという。スタッフにムリをさせられず、売上げも考えなければならない。でもいまは、自分らしい菓子をつくることだけを考えればいい。
とはいえ、最初から売れていたわけではない。開店後1年半は、ケーキを捨てる毎日が続いたという。売れない当初は不安でいっぱいだったことを、杉野氏は隠さない。そして阪神大震災。だが、
「だから売れるケーキをつくろうとは、ぜんぜん思わなかった。売れるケーキをと思えば、どこも一緒になっちゃうでしょ」
ときっぱり言う。断面がきれいに出るなど、大きな型でつくるほうがいいもの以外は、一つひとつの小さな型でつくるケーキが、この店では多い。断面が見えて中が何であるか分かると、意外性も薄れると、小さな菓子に杉野氏はこだわる。小さな容量の中に複雑な構造で、かつバランスをつくっていくのが、杉野氏らしいのである。
杉野氏は、料理を食べ歩くのが好きである。日本料理でさえも、たとえば旬の富貴豆の風味を味わいつつ、豆のくさみを消して風味を残すにはどんなハーブが合うのだろうなどと、いつも味の組合せのことが頭をよぎる。料理本もよく読む。おいしそうなデザートなどあれば、かならずつくってみるし、アレンジもする。そんなくり返しの中で、ヒントが生まれるのだ。杉野氏の持論はこうである。
「料理人が使う素材の数は、菓子職人の比ではないのです。知らない味、知らない組合せはまだまだいっぱいある。僕らは肉こそ使えないけれど、どんな味や組合せがあるのか、いろいろなものを多く味わうこと、見ることが、本の中であれ、お店であれ必要だと思う」
商品化の際には、試作を重ねて、濃さ、量、食感とも、もっともいいと思われるバランスを決める。こうして個性が加わった菓子は、どれも可愛いという。だから、ひとつが売れても、それだけをたくさんつくることはしない。どれも同じくらいずつ並べている。
杉野氏はいま、自分の店をめざしてわざわざ来てくれるお客に満足してもらうために、菓子をつくっているのだ。
■杉野英実(すぎの・ひでみ)
1979 ― 1982年在欧。フランス・アルザス、スイスのホテルやレストランでデザートを担当。パリの名店「ジャン・ミエ」、「モデュイ」、「ペルチエ」(2004年に閉店) で当時の最新の菓子づくりを吸収。1992年に神戸・北野に「パチシエ イデミ スギノ」を開店。2002年12月に東京・京橋に移り、「イデミ スギノ」として営業、現在に至る。技術向上をめざす欧州の菓子職人の組合「ルレ・デセール」の会員。既刊に『素材より素材らしく』『杉野英実のデザートブック』(ともに柴田書店刊)がある。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)