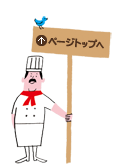オーソドックスな商品こそこだわるべき

「記念すべきひとときのために、私どもは技と創造性を調和させ、忘れられない味をお届けします」
こんな心に響く言葉が、ルレ・デセール協会のガイドブックの「ヴェルニュ」(フランス・フランシュ・コンテ地方オーダンクール)のぺ―ジに書かれている。
生ケーキから焼き菓子、チョコレート、アイスクリーム、それにトレトゥール(惣菜)と総合的に手がける店で、その土地の人々にとっては、結婚式やクリスマス、記念日、子どもの洗礼式などの祝い菓子を飾る店。クリスマスやイースター時期の店内はお客でいっぱいとなり、ストックルームには細かく分類された商品の高層ビルが建ち、その間を売り子やパティシエがせわしなく動きまわる。記念すべき行事の注文が入るたび、時には夜を徹しての製造にパティシエたちは大忙しとなる。
ヴェルニュの店はそんな典型的なフランスの高級菓子店。ただし、味は典型の枠に収まらない。格別なのである。
まずなんといっても焼き色がよい。タルトの生地、クロワッサン、クグロフ、ケイク(バターケーキ)など、お菓子の焼き色を大切にしている。
2代目オーナーシェフ、エリック・ヴェルニュ氏いわく、
「窯とはパティシエの魂のようなもの」
焼き色が白っぽかったり濃すぎたりすればお菓子のおいしさは漂ってこない。つまり焼き方ひとつでお菓子の表情はがらりと変わるものだ。ヴェルニュ氏のお菓子は飾りたててコケティッシュに仕上げたそれではなく、健康的な素肌が美しい、そんな表情だ。だから味わってみたくなる。するとヴェルニュ氏の味の核心がひと口ごとにみえてくる。
タルト・クラフティ・オ・スリーズ。サクサクした生地の中にグリオット(チェリーの1種)がたっぷり入っている。ひと切れは割と大きめだが、グリオットの酸味がきいているので重たくは感じない。(中略)
素材のよさはいうまでもない。
クリーム、バターはすべてエシレ産、牛乳は搾りたてをそのまま使う。フルーツはローヌ・ヴァレー地方の最高品種を選び、チョコレートはヴァローナ、トレトゥール部門に使う魚などはブローニュ・シュール・メールの港に揚がったものを夜行便で直送させる。
完璧主義。原料が届いてから商品としてショーケースに並べるまで、最初から最後まで力を抜かない。
「チョコレート・エクレア、クロワッサン、ショソン・オ・ポム、この三つはどんな店にでもある。価格帯も低く、常に一定の売れ行きを確保できるだけに、つくり手側も気を抜きやすい。だが意外にもこの三つを食べればその店のレベルが分かってしまう。まずチョコレート・エクレア。よいチョコレートを使っているかどうか。それにクリームの食感で技術的な程度が分かる。クロワッサンは生地の仕込み方や使っているバターの質でみる。ショソン・オ・ポムについては、中身のリンゴの火の通し加減で知ることができる。いい加減なところでは、生のリンゴではなく缶詰のものをそのまま生地に入れていたりする。高く売る商品だからきちんとつくるというのでは職人としてあまりにお粗末。どこにでも売っているからこそ競争も激しいし、完璧に仕上げるにはそれなりの意識が必要だ」
ヴェルニュでは、オーソドックスなアイテムだからこそ素材、焼き色、つくり方から仕上げ、すべての段階をきちっと踏みしめてお菓子をつくる。味わった時につくり手の技術、こだわりが味覚と嗅覚を通じて伝わるのだ。
思い出に残る味づくり、人生の節目を祝う食卓にのるお菓子は、こうあるべきかもしれない。
7歳頃から仕込まれたパティシエ修業
エリック氏の父ジョルジュ・ヴェルニュ氏は70年代にガストン・ルノートル氏に師事し、それがきっかけで味、質を追究したパティスリーの構築に目覚めたうちのひとりだ。その時の仲間がアルザス「ジャック」のジェラール・バンヴァルト氏や、パリ「ペルチエ」の創設者リュシアン・ペルチエ氏などである。
ルノートルの考え方に強く影響を受けた父ヴェルニュ氏。エリック氏は幼い頃から、菓子づくりに対する父の情熱を真横で感じていた。
「完全を追求する姿勢、それに豊かな創造性。父の店が仮に惰性で仕事をしているようだったら、私はパティシエの道をおそらく歩まなかったと思う」
父ヴェルニュ氏はエリック氏に、7歳くらいの頃からパティシエの仕事に接する機会を与えた。学校の授業がない水曜日には、小さなパティシエは厨房に入る。彼に与えられていた仕事はマカロンを貼り合わせること、作業台や厨房のそうじなどだった。次第にエリック氏は子どもなりに考えて仕事をするようになった。
「まず冷蔵庫を開けて天板が何枚あるか数える。何時に仕事を終えるか見当がつくから、友だちには何時頃に行くからねと約束ができる。仕事を終えずには遊びに行くことも許されなかった。友だちのパーティに呼ばれている時でさえも同じだった。父の口癖は『お前が仕事を終えていく頃にはちょうど雰囲気が盛り上がっているだろうから、一番いいタイミングで参上できるじゃないか』。こうやっていつも説得されてしまう」
厳格な父に育てられ、エリック氏は職人としての基盤を徐々に固めていった。一流の職人である父、販売を仕切る母、明けても暮れても仕事に情熱を注ぐ両親の姿。エリック氏には誇りだった。が、そこには寂しさを耐えている少年の姿もあった。
アプランティ(見習い)として本格的に仕事をはじめる前に技術的なことのほとんどを父は覚えさせた。いずれは店を継ぐことを考えると、経営に役立つ知識も必要となる。高校卒業後に会計学のバカロレア(国家資格)に合格したのち職人の道に入り、CAP(職業適正証)を取得した。つまり高学歴の大学生が中学3年生や高校1年生くらいの若い世代に混じって、2年間パティシエになるための基礎的な勉強をしたのである。
CAP取得後のパティシエとしての第一歩はアルザス「ジャック」ではじまる。バンヴァルト氏のもとで1年間働いた。
エリック氏の父とバンヴァルト氏はルノートル時代からの仲間。豊かなお菓子づくりのために本質を追究する姿勢を、エリック氏は父以外の職人からも肌で感じとることになる。父同様に仕事に対して厳しいバンヴァルト氏からは経営センスの重要性も学んだ。
ジャックを辞した時、エリック氏は兵役の務めを果たさなくてはいけない年齢に達していた。フランスでは、成年男子には兵役が義務づけられている。成年となる18歳から定められた年数の間に、勉学や仕事を中断して兵役につかなくてはならないのである。ただし誰もが武器を持たされるということはなく、特殊技能のある者はそれに応じて任務が与えられる。エリック氏はそのケースで、首相官邸マティニョン宮のパティシエとしてのポストを与えられた。
当時の首相は後に大統領となったジャック・シラク氏。首相が主催する要人を招いてのレセプションやバンケットで供されるお菓子やデザートをつくった。この経験が若いエリック氏にパティシエの仕事への誇りをもたらしたことはいうまでもない。
兵役を終えたエリック氏はパリに残り、「ペルチエ」「ダロワイヨ」といった名店で修業を重ねた。「ダロワイヨ」ではパティシエのポストを希望していたが、あいている仕事はトレトゥール部門だけだった。しかしエリック氏はあえてそのポストにつく。製菓よりも料理の分野に近いトレトゥール部門を経験し、それが新たな視野を広げるのに役立ったのだ。
現在ヴェルニュでは、家庭での小規模なパーティから1000人規模のバンケットまでわずか12人の厨房スタッフで製造をこなす。
パリでの修業を終え、エリック氏は故郷にもどった。結婚したばかりのコリーヌ夫人をともなっての帰郷だった。そしてすぐにベルフォールの街に売場のみの「ヴェルニュ」2号店をオープン。店舗の総面積は増え、従業員も倍になる。20㎞離れた店には週末の忙しい時には日に3回も搬入を行なう。製造、スタッフの教育、経営など、店という概念から企業へと変化する時がきたのだ。
そして15年余りがすぎ、2000年5月に父は現役を退いた。ヴェルニュの2代目として、パティシエという立場に加え、総合的に仕事に取り組む姿勢の重要性をエリック氏は重く受け止めた。
「アプランティひとりから店をはじめた父は、なにしろ可能なところまで店を発展させた。だから私が入った時点では事業としてはすでに成熟しきった状態。スタート時点が高いわけだから、これを後退させることなく維持し、さらに発展させなくてはいけない。そこが2代目としてつらいところだと実感している。父の世代では、気力があり、時間を惜しまずよく働くよい職人でいることがある意味では理想とされていた。でも現在ではよい職人でいるだけではすまされない。マネージング、PRにもセンスが求められる。菓子店といえど、より総合的でないと存続はむずかしい時代。自分の店の現在の欠点はCI(企業イメージ)が弱いことだ。こういったことは外部にためらわず委託して、能力ある人と協力して改善すべきだと思う。父などは根っからの職人だから店に出ることはほとんどなかったが、私は積極的にお客にも接するようにしている。そんな時『先日のお菓子とてもおいしかったです。おかげですてきなお祝いができました』とお礼をいわれたりすると本当にうれしい。両親がそうしていたのとは違って、いまは仕事に犠牲を払う時代ではない。仕事から得られる感動やさまざまな知識、それらで自分の人間性も豊かにしていきたい。製菓のテクニックや経営の理念にしても、現在われわれが正しいと思っていることが未来にそのまま通用するとは限らない。父の20年前の仕事と私の10年前の仕事、そしていまとではその内容は違う。がむしゃらに働くのではなく、時折荷物を下ろして、時代が求めるものをしっかり見極めてから進みたいと思う」
ただし時代が変わろうとも、ヴェルニュの味は恒久的に幾世代もの人々の味覚を喜ばせ続けるだろう。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)