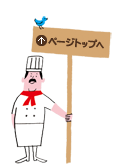菓子は手づくりが本来のあり方

「訪れる誰もがまず最初にそう思うようです」
とこの店の店主は笑う。歴史的建築群が建ち並ぶ音楽の都、バロックの都と謳われるあのウィーンの印象はこの辺りにはない。ここ20区は外国人労働者が多く住む場所のひとつ。行き交う人々の顔だちや髪の色、服装などに異国を見ることができる。最近、近くに地下鉄の駅ができたが、通勤時間帯以外の乗降客はまばら……。お世辞にも好立地とは言えない。そんな場所に誰もが驚くという。
しかし、この環境の中にある「カフェ・コンディトライ(菓子店の意味)・ディートマー・フェルヒャー」の主人、デイートマー・フェルヒャー氏の名をウィーンの菓子業界で知らない者はいない。いまは現役を退いたが、その卓越した技術と味のセンスでウィーン菓子をふたたび世界レベルに向上させた、かのカール・シューマッハ氏が、新しい世代のリーダーとして推すのが、フェルヒャー氏なのである。シューマッハ氏同様、フェルヒャー氏がつくり出す味には伝統的な菓子であっても、従来の「甘い、重い」といったイメージはない。
たとえばザッハートルテ。ウィーンではその店のザッハートルテを食べれば、職人の腕がわかると言われる。分量は別にして、使う材料が法律に定められている。バター、粉糖、卵、グラニュー糖、クーベルチュール(チョコレート)、水、塩少し、それに生地と上がけのチョコレートとの間に使うアプリコットジャム。これ以外の材料を使うと、ザッハートルテという名称はもう使えない。同一の条件なので、比較がしやすいわけだ。フェルヒャー氏のそれには定評があり、特別注文もザッハートルテが多い。が大量の注文が入って急ごうとも、テンパリング技術の基本はしっかり守る。「つやが目においしさを訴えかけ、舌触りもやさしくなるから」だという。
元祖を名のる老舗に比べ、確かに粗雑なザラつきがない。しっとりしたチョコレート風味の生地にアプリコットジャムが湿り気を与え調和しているのが、「妙」である。こんな不便な場所でも、この味ゆえにお客は集まってくるのだ。軽くて繊細な味わい。それでいて素材自体の風味はしっかり感じる。それが、フェルヒャー氏の持ち味。これは、当初からある独自の「こだわり」から生まれたものだ。
ディートマー・フェルヒヤー氏。1953年、オーストリア南部、イタリアと旧ユーゴスラビアに国境を接するクラーゲンフルト州に生まれる。隣家の息子がパティシエで、帰郷のたびに彼からお菓子のこと、外国での修業の話などを聞かされていて、自分も菓子職人になろうと思う。義務教育の最後の年、14歳の時であった。
まずは名人の味を舌で盗み、次に舌の記憶でその味を再現。それから自分の味をつくり比較する
当時、オーストリアは日本と同様、経済発展期。菓子業界でも、大がかりな機械化や設備投資をするところが目立ってきていた。繊維業界で天然素材より化学繊維がもてはやされたように、菓子業界でも加工品や添加物などを多用するのが流行っていた。フェルヒャー氏が最初に見習いとして入った店も、機械化、合理化の方向に走っていた。就業時間は長く、これを規制する法律もまだできておらず、1日10時間以上働くことはしばしばあったという。
見習いの3年間は店で働くばかりではなく、週に2、3度は州立の職業学校に通う義務がある。ここでは外国語などの一般教養や菓子づくりの基礎理論、実技などをみっちり教え込まれる。
「店での労働はハードでしたが、体力と忍耐力を培うことができました。その反動ではないですが、学校ではすべてを吸収してやろうと必死に勉強しました。店では機械がやってしまう基礎的な作業も、学校では教えてくれる。手作業でなくては出せない味や、材料のデリケートな配合や素材を吟味する方法も学校で学びました」
とフェルヒャー氏。「まずは基本から」というのが彼の座右の銘だという。機械化、合理化の中での修業時代だからこそ切実に基本の大切さを痛感していた。そんな彼の考え方を決定づけたものに、先述のシューマッハ氏との出会いがある。職業学校時代のこと。が、直接シューマッハ氏から教えを受けたわけではない。勝手に学んだのだ。
オーストリアでは職業学校修了後に一人前の職人としての「マイスター」の受験資格が与えられる。その受験生のための特別講座の講師としてある期間、シューマッハ氏が招かれていた。フェルヒャー氏は昼休みに店をこっそり抜け出し、シューマッハ氏の実技授業をのぞいた。受験生たちの試作品を観察し、味見までしていたのだ。
「一つひとつの素材自体を味見する他、材料を混ぜ合わせるたびに自分の舌で味を確かめることをシューマッハ氏から学びとりました。材料はいつも同じ状態ではあり得ない。しかし、でき上がりの味は均一でなければならない。だからつくる工程の要所要所で、自分の舌で、自分の求めるものになるように味を確かめるのです」
それによって個性も出せると、フェルヒャー氏は主張する。まずは名人と呼ばれる人々の味を舌で盗み、次に自分の舌の記憶で試行錯誤してその味どおりに再現する。それから「自分ならこうする」という味をつくって比較する。こうして独自の味をつくってきた。
フェルヒャー氏の店の人気商品のひとつにヒンベア・モーンシュニッテ(Himbeer Mohnschnitte)がある。生地はモーン(黒ケシの実)をたくさん入れたバターケーキ。上には大粒のフランボワーズがのり、フランボワーズ風味のシロップにゼラチンを溶かしたもので固めてある。その上がけと生地の間にはホイップした生クリームを挟み、上からじんわりと降りてくるフランボワーズ風味のシロップが生クリームの防湿作用と相まって生地にほどよく染み込み、独特の味わいを醸す。ほのかなモーンの香りと口溶けのいい独特の食感。ゼラチンには塩をわずかに入れて甘さを引き立て、果汁の酸味を適度にまろやかにしている。多重の味わいがあるこのうれしい感動は、つくる過程での味見なしには完成しない。
フェルヒャー氏は、職業学校修了後にマイスターの資格を取得すると、ウィーンの東方200kmにある上オーストリア州の州都、リンツの菓子店「ニメッツ」に職場を移す。ここは当時シューマッハ氏がシェフをしていた店。国内外からいつも職人が修業に来ていた。ここではじめてシューマッハ氏との実際の師弟関係が生まれる。
「ニメッツ」に勤めて1年後、オーナーから国外で修業することを勧められる。シューマッハ氏が紹介してくれたイギリスのホテルで、シェフはオーストリア人。フェルヒャー氏はデザートに関心を持っていた。ここで彼はデザートのレパートリーを増やすことになる。
フェルヒャー氏は、ハプスブルク王家時代からの伝統的な「ヴァルム・ズースシュパイゼ(Warm Süßspeise。温かな菓子。食事ともなる)にも着目した。コーヒータイムに、また単独の食事のコースとして、あるいは食事の後のデザートとしても出されるこの伝統的なウィーンの菓子を大切にしようと考えていた。さらに地方の家庭に残る素朴な菓子にも以前から興味があった。こうしたお菓子にプロの技を加え、ホテルのデザートとして提供することも試みた。
「ヴァルム・ズースシュパイゼなど昔からあるレシピを、コーヒータイム、食事の後といった時間帯に合わせてアレンジしました。本来の味は舌にたたき込んであったので、アレンジはさほど冒険ではありませんでしたね。食後のデザートとしては、お客さまのお腹が満たされていることを考慮し、視覚的な美しさを狙ったデコレーションなどもこの時、研究しました」
75年シューマッハ氏から声がかかり、今度はウィーンのホテル・ヒルトンのシェフに就任する。22歳の時であった。さらに翌年はドイツ・デュツセルドルフのヒルトンヘ。77年、ウィーン市が市のはずれの地オーバーラーに広大な温泉保養地を造成。その中に「カフェ・コンディトライ・オーバーラー」が、シューマッハ氏をシェフとして開店し、フェルヒャー氏は副シェフとして迎えられた。
同店では場所柄砂糖を控えて軽めにお菓子を仕立て、良質の素材を使うことにした。商品は、シェフをはじめ見習いまで一緒に意見を交換して考えられた。シューマッハ氏率いるオーバーラーの名は、またたく間にウィーン市はもとより国外まで知れわたるようになる。
ピカソにデッサン力があったように、菓子づくりにも基礎技術が大事
この仕事の後、81~84年までフェルヒャー氏はふたたびウィーンのヒルトンヘ。そして84年にはミシュランから星をもらったホテル・インペリアルのレストラン「コルソー」へ移り、さらに2年後には同ホテル系列の「カフェ・ツェントラル」のシェフとなった。
この頃フェルヒャー氏は、ヴァルム・ズースシュパイゼを中心にした『Desserts(デセアー)』、オーストリアの代表的な菓子のレシピ集『Die feinsten Mehlspeisen(ディ・ファインステン・メールシュパイゼン)』を出版。自分の菓子づくりの思いをまとめてもいた。数々の一流店を歩いてきて、また国際的なコンテストにも国代表チームで参加し、数々の栄誉に輝いたフェルヒャー氏ではあるが、この時、自分の手づくりのお菓子を堪能してもらい、お客の声がじかに聞ける、そんな空間での菓子づくりをしたいと思うようになっていた。
90年、やっと夢が叶って自分の店を持つ。場所柄、酔っ払いは入ってくるし、昔ながらの重い味ではないと評する地元客もいた。それでも半年もすると、今度は批判した地元客が常連になってきた。価格はロケーションを考えて極力抑えているが、素材へのこだわりに変わりはない。材料の仕入先はオーバーラーやホテル・インペリアル時代からの業者も多いという。「一 度食べてみればわかってくれる」という信念があり、だから遠くからでも来てくれるよと淡々とフェルヒャー氏は語る。職人気質を感じさせるひと言である。
顧客は増え、市外からもわざわざ訪ねて来てくれる。特注するお客も多くなってきた。が、事業を拡大しようとは考えていない。
「手づくりが本来の菓子のあり方。よい材料を吟味しておいしい菓子をつくるのが、職人の使命です。大きくしようとは思わない」
彼の店で学ぶ見習生については、穏やかな□調でこう評する。
「若い人たちはデコレーションのセンスは素晴らしいのですが、肝心の味を忘れている人も多い。素材の吟味と基本技術を大切にすることを心がけさせています。たとえばピカソの絵。彼は基礎、つまりデッサン力があったからこそ、大胆なデフォルメをした作品が評価されるのです。菓子づくりも同じことです」
フェルヒャー氏のケーキはみかけはいたってシンプル。が、素材を生かしたきめ細やかな味わいだ。それはカフェで提供する「温かな菓子」にも表われている。たとえば卵黄たっぷりの小さなパネトーネ風菓子にバニラソースをかけたドゥカーテンブフテルン(Dukatenbuchteln mit Vanillesauce)、トプフェン(チーズ)をパイ生地で巻くミルヒラームシュトゥルーデル(Milchrahmstrudel mit Vanillesauce)、パンケーキをほぐしたような生地をリンゴのムースで食べるカイザーシュマーレン(Kaiserschmarren mit Apfelmuß)、トプフェンを使った団子にフランボワーズソースをかけたトプフェンクヌーデル(Topfenknödel mit Himbeersauce)など。どれも軽くて品があり、それでいて伝統の味は損なわれていない。
「人々の嗜好はこの数十年で大きく変化してきた。しかし、基本の味は崩さない中で、いま求められる味を表現することが大切です」
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)