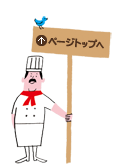トロワグロとの出会いが今の私を作った

前のページで紹介したベルナール・ロワゾー(→ http://www.ss-foodlabo.com/quotation/quotation_detail?id=60 を参照)と、ここで紹介する、パリ一六区で自分の店を経営するギー・サヴォワとは、二つの共有する出会いがある。
その第一は、二人とも料理人としての出発であるプランティ(見習い)を『トロワグロ』で行なったということである。しかも二人は、一年間は先輩、後輩として同時期に『トロワグロ』の調理場にいたのである。
第二はクロード・ヴェルジュという料理人(というよりはいくつかのレストランを持つ資本家といったほうがいいかもしれない)との出会いである。
ロワゾーは前ページでもふれたように、『バリエール・ドゥ・クリシー』で料理長となり、『コート・ドール』に至るまで、このヴェルジュを育ての親として一緒に歩んできた。そしてギー・サヴォワも同じ『バリエール・ドゥ・クリシー』でクロード・ヴェルジュと出会い、その才能を開花させたのである。
このように、いわば『トロワグロ』で産湯をつかい、ヴェルジュという名介添人の力で自分の才能を発揮することができた二人が、その個性の違いによって、その後それぞれがどのように成長していったかを考えることは、まことに興味深いものがある。
ギー・サヴォワの母親は、リヨン郊外で小さなレストランを経営していた。そうした環境で育ったサヴォワが、料理に対する興味を小さいうちから持っていたことは何の不思議もない。とにかく料理人になりたかた少年ギーは、まずニースのホテル学校の入学試験を受けたのだが、残念ながら落ちてしまう。
ちょうどその頃、母親の友人がトロワグロ兄弟を紹介してくれるという幸運が飛び込んできた。「試験に落ちたことがかえってトロワグロに会えることになった」というめぐりあわせに感謝しながらギー少年はトロワグロに会いに行った。その時、料理をする前に菓子を勉強するように、とのアドヴァイスを受けた。
そこでパティスリーに入り、一年間菓子の勉強をした後、ようやく『トロワグロ』の調理場にアプランティとして入ることを許されたのである。
やりたいことのすべてがトロワグロにあった
今まで私が働いたレストランの中で、私が一番影響を受けたのは、何といってもトロワグロ兄弟でした。仕事のことはもちろん、人間的な面でも多くのことを学びました。特に接することの多かったジャン・トロワグロは、あれだけの名を揚げていたグラン・シェフなのに、決して調理場を離れずにソースを仕上げている、その姿は私に料理人としてのひとつの理想の形を刻みつけてくれました。
ここの店は調理場が狭いし、第一自分の店なのだから調理場で仕事するのは当たり前ですが、たとえ店が大きくなっていっても、同じように調理場に立ち続けるシェフでありたい、と思っています。
トロワグロの調理場で、料理の点で驚いたのは、材料がとても新鮮だ、ということでした。それほど新鮮で良質な素材というものを、それまで私は見たことがありませんでした。
そして、すべての料理が実にシンプルに作られていたことです。そのシンプルさの偉大さは、現在になってもそのすごさを仕事の中で感じとることがあります。
もし私が他の店で料理を学び始めていたなら、きっとこの仕事は続けていなかったのではないでしょうか。そのくらい、トロワグロとの出会いが、今の私を作った、といえるのです。(中略)
※ベルナール・ロワゾーは、私たちに、ボキューズやゲラールそしてトロワグロといった〝一世代前の達人たち〟を自分たちはすでに乗り越えて、新しい自分たちの時代がやってきた、と高らかに宣言した。一方、ギー・サヴォワはトロワグロへの畏敬ともいえるような想いを静かに語っており、その違いがはっきりと出ている。
別に他の店が良くないというのではなく、私の料理に関するすべてのものがトロワグロにあり、自分のやりたいと思うことのすべてがトロワグロにあったのです。
最高のコンディションで最高の材料を見つける
――その尊敬するトロワグロの世代の料理人が、若い料理人たちは基礎を知らなすぎる、もう一度古典をふり返るべきだと主張する風潮が、ここのところ強い。
どうなんでしょうね……もう少し彼らも控えめになって今の現実というものを受け入れるべきだとは思いますよ。でも、若い料理人の中には、本当にいい加減な仕事をしている人が結構いるんです。
だから先輩たちが、お前たちは道からはずれているぞ、と言う時、あるいは新しい世代を攻撃している時、それはいつも本当のプロの若い世代に対してではなく、きちんとしたベースを持たず、いい加減にセンセーショナルにやっている連中に対して言っているのだ、と思っています。
いつの時代にもリーダーと、それをコピーしようとしてうまくできずに、まったくナンセンスなことをする人はいるものです。そうしたいい加減さは攻撃されるべきであって、若手への先輩たちからの忠告は、決してロワゾーやマクシマンといった才能ある料理人に向けられているのではないですよ。
そう、ジャーナリストは好きなことをいいますからね。でもそれはそれでいいのであって、料理人がそんなことに動かされなければいいんですよ。
どんな店のどんな料理人だって、ある程度のベースを持って、その上で本当に料理を作りたいと思いながら作っている人の料理は、絶対に美味しいものなのです。
私にしても、私がやりたいように、思うようにして、それでお客さんが満足してくれるなら、この他に何が必要でしょう?
――トロワグロ、ロワジスなどで修業したギー・サヴォワは、七九年までの三年間『バリエール・ドゥ・クリシー』の料理長であった。料理界にデビューしたての時のすぐに『ゴー・ミヨ』がギーを非常に高く評価していたことは印象的であった。
「ギー・サヴォワは古くからの知り合いである。無名のこの若い料理人が、バリエール・ドゥ・クリシーの調理場で働くようになってまもなく、私たちは三ツ帽とクレ・ドールを与えた。それほど彼の才能はきわだっていた。周りも当然そうなるものと予想していたが、彼自信も自分の店を持ちたくなり、小さな店を買い取った。(略)トロワグロとウーチェの所で修業を積んだこの二七歳の若者は、料理のあらゆる微妙さ、繊細さをつかみ、その構想はとてもモダンであり、しかも気取りがない。彼は変化のない、惰性のカルトの限界に自らを閉じ込めない」(ゴー・ミヨ、81年度版より)
八〇年に独立、ゴー・ミヨは当然三ツ帽を、ミシュランも翌年には一ツ星を与えている。
バリエール時代の料理は、今はもう作っていません。私自信が変わりましたし、前進もしていると思っています。五年後にはきっと今の料理とはまったく違った料理を作っているはずです。
パリで料理を作るということの意味ですか? その土地土地に特徴的な産物があり、それを使ってその土地の独特な料理を作っている人もいますが、パリはそうした意味では、とにかくどこの産物もみんなパリに入ってくるわけだから、パリの料理はフランス各地の料理を集約したものといえるかもしれません。
でも私にとっては地方性というようなことはどちらでもいいですね。それよりもその時その時に、最高のコンディションで見つけた最高の材料を使って、最高の自分の料理をつくることのみ意味があるのであって、太陽や風で料理するわけではありません。
材料さえいいものが手に入れば、いつでも私の料理は作ることができます。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)