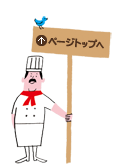当意即妙。魯山人と星岡茶寮の料理

調理場での修業を何段階かジャンプして進む
私は岡山県の笠岡という町から一里ほど田舎に入ったところで生まれたのですが、伯母が笠岡で遊覧船や貸ボートなどを手広く営んでいまして、一六歳の時にその店の手伝いに入るのです。笠岡という町は瀬戸内海をひかえていますので結構、花界隈も発達していましてね。漁師も多いし良い魚も獲れるということで料理屋なんかも結構多かったのです。ですから料理屋の客が仲居さんや芸者さんを連れて夕涼みに遊覧船なんかに乗りにくるわけです。ということは伯母の店を利用したツケがたまるわけで、身内である私が集金なんかをやらされるんですね。
その笠岡の町に「伏源」という町一番の料理屋がありましてそこの大将が、私が集金する様子をどこからか見ていたんですね。「あのボンさんはなかなかしっかりしている。ああいうボンさんが店(うち)に来てくれたらな」という話が、私に聞こえてきたんです。ちょうど私も、何か違う仕事をしたいなと思っていた矢先でしたので、その料理屋に働きに出ることが、トントン拍子で決まったのです。
これが私が料理人になるキッカケです。最初は調理場に入ったわけではなくて帳場の仕事を手伝っていたのですが、帳場から調理場を見ていますと、実に楽しそうに仕事をしているんです。それで何とか料理をやりたいと思うようになりまして、料理長に直訴したんです。そうすると「やめておきなさい。料理人という商売は道楽商売みたいなもんで、あんたには合わない」というんですね。店の大将にも頼んでみたんですが、やはり同じように「確かに料理人という仕事には酒、女、バクチがつきまとうし…」と乗り気じゃない。でも私は、言われれば言われるほど料理人になりたくって「料理人のみながみな道楽商売のように仕事をしているわけもないだろう。まして私は料理が好きで、その道を極めたいと思っているのですから」とひきさがらなかった。結局、そんなに言うならということで、許可が下りたのです。
そんなわけで調理場での仕事を始めるようになったのですが、帳場で仕事をしながら料理人さんたちの手の動きをいろいろ見ていましたので、それが結構役立ちました。たとえば瀬戸内から活けの穴子が入ってくるのですがそれを水洗いしているボンさんがよく失敗しているんです。見ていますと、穴子を叩く場所にこつがあるんですね。そこを正確に叩くと穴子は一瞬気絶するんです。そこで一気にさっと裂く。そんな姿を見ていましたので、料理長に頼んで穴子を裂かせてもらったのです。ある程度こつは見て覚えていましたので、ほとんど失敗もなく裂けたもんですから料理長が驚いてボンさんに「お前たち見てみろ。今日初めて穴子にさわる松ちゃんがこんなにうまく裂けるんだ。お前たちは何年同じことをやっているんだ」と言って、私のスジがいいと褒めてくれまして……そんなことで料理長が私を認めてくれるようになったのです。(中略)
このように料理が根っから好きだったんでしょう、ここというポイントは自分なりにつかみながら仕事をどんどん覚えていったのです。都合五年間、この店で料理の基礎を学んだことになります。
ツテ、コネを頼りに魯山人に会おうとする
この五年間の締めくくりに、実はロマンスがあったんです。修業先の料理屋の娘さんなんですが、この女性といい仲になり、夫婦約束までするのです。ところが私は使われている身ですし、周囲がいろいろとうるさいもんですからとにかく一度、東京に出て一年後に帰ることにするから、それまで待ってくれ、さびしいが一年間だけがまんしようということで、私は上京するわけです。九歳上の兄が早稲田大学を出て新聞記者をやった後、佐藤春夫さんについて小説の勉強をしていたので、とりあえず兄のところに世話になることにしたのです。
兄は吉川英治さんとも親交があって、私はブラブラしていたもので、たまには吉川さんのところで料理を作ったりと、気儘な日々を送っていました。しかし、せっかく上京したのだし、ただブラブラしていてもしょうがない、どこか料理屋に勤めたらどうか、ということになりまして、心当たりを探し始めました。当時、築地の「錦水」という料理屋があったんですが、ここは待合みたいなものなので、やはり料理屋といえば「星岡茶寮」だろうというのが兄たちの意見でした。「しかし星岡はちょっと入れないぞ。相当のツテかコネが必要なはずだ。ことにこの料理屋には魯山人という大変な人がいて、この人の目がすべてにゆき渡っていて、その魯山人がうん、と言わない限り無理だろう。第一、あそこに入るには試験もあるというぞ」ということなんですね。(中略)
さて、下宿していた飯田橋から電車に乗って赤坂山王下まで行き、山を上がっていって星岡茶寮に魯山人を訪ねる日がやってきます。当時の魯山人は、いわば絶頂期で、鎌倉と東京をいったり来たりしていたのですが、幸運にも訪ねた日に、魯山人は星岡にいたのです。私は中村三郎という、件の女性(魯山人にはキャバレーに勤めるお気に入りの女性がいた)の弟を訪ねて星岡茶寮の門をくぐります。そして、調理場の上にある、魯山人の部屋をいよいよ訪ねるわけです。
魯山人の部屋は総ガラス張りで、調理場が見渡せるようになっていました。その部屋の大きな回転イスに、魯山人が背中を見せているのを確認して部屋に入ります。「初めまして、岡山から来た松浦と申します……」と挨拶するのですが、魯山人はまったくこちらを振り向きもせず、うんと言ったきり一〇分くらい何も言わない。吉川英治さんの紹介状を魯山人の脇に差し出しても、見ようともしないのです。
ようやく背中を見せたまま「東京に料理屋がたくさんあるのに何故、星岡を選んだのか」という質問が沈黙の中から返ってきました。「星岡茶寮は日本一の料理屋だとうかがったものですから。どうせ勉強するなら日本一の料理屋で勉強したいと思いました」「うん」それからまた無言です。ようやく私の履歴書に目を通し、一言「月給はいくらいるんだ」。「日本一の料理屋で働かせていただけるなら、月給がいくらなどと注文はありんません」「うん」そして初めて回転イスを回して私の顔を見てくれたのです。
最初に魯山人の顔を見た時は、その大きな顔、大きな耳、鋭い眼にびっくりしましたね。そう思うか思わないうちにベルがビーンと鳴って私は飛び上がるほどびっくりしました。イスの下にあるボタンを魯山人が押したんですね。やがて階段をトントンと上がる音がして白衣の料理人が私の前に姿を現します。当時の料理長、竹山一太さんでした。
魚のアラでのテストで評価され、椀場に抜擢
当時の星岡茶寮は職人が一〇数人、京都の瓢亭、大阪のなだ萬というように一流の店の出身者で固めていました。それら職人の助手として若い人、さらに研究生として全国各地の料理屋の息子たちが三ヵ月、六ヵ月、一年といった具合に期限つきで勉強していました。そうした地方の料理屋の息子がいるお陰で、居ながらにして地方の名産、珍味が集まるわけですから、さすが魯山人、頭のいいやり方をとっているなと思ったものです。
私は特に何をやれと言われないまま、その日から調理場に入って働き始めました。といっても場を与えられていませんから煮方や焼き方、板前の仕事をじっと見ていながら忙しい時にちょっと手伝うというくらいで半月が過ぎたわけです。しかし、すでに五年の経験がありましたから、見るだけでも大変な勉強になりました。
ある日、突然、これから魯山人が鎌倉に行くので材料を持ってお供するように、それが試験だと言われました。問題は何を材料に持っていくかです。何と虎屋の箱に魚のアラばかりがびっしり詰まっていたのです。タイもありましたがハモ、コチ、アイナメ、その季節の魚のアラを三箱詰めて持っていったのです。もちろん魯山人がそのように指示したんです。普通、試験をするといえばタイならタイを一尾持っていって、いろんな料理を作るように指示するところでしょうが、さすが魯山人は違う。魚のアラを使ってどういう料理を作るか、いかに味付けるかがテストだというわけです。言われるとなるほど、と思ったものです。この人は世評どおり、一味違うぞと思って緊張したことを覚えています。
車に乗って魯山人、秘書、そして私というメンバーで鎌倉に向かったのですが、鎌倉に近づくと誰にも話すともなく、「ここに豆腐屋があるな」「魚屋もこの辺にあったな」とつぶやいているのです。後で気づいたのですが、結局私がどれくらい、そうした細かいことに心をとめられるかを試していたんだなと思いました。
さて、鎌倉に着きますと、今夜六人の客があるので、その準備をするように、と言い渡されました。前の畑には菜っぱやネギなど、いろんな野菜が植えてある。戸棚には乾物があって、湯葉、高野豆腐、ヒジキなど入っている。そんなことを私に教えて自分の部屋に入っていってしまいました。さあ、時間はないし、とにかく時間までに料理を間に合わせなくてはならない。三時間くらいしかなかったのですから。タイは吸いものにしました。ハモは白焼きにしてから、女中頭に焼き豆腐を買ってきてもらって一緒に炊き上げ、ショウガを絞って熱々を出しました。あれやこれや工夫して何とか七~八品は作りましたかね。ところが最後にもう一品できないかとの注文があった時には冷や汗がでました。
それでも女中頭が「今日はいつになく先生もたくさん召し上がった。お客さんも大変満足の様子でしたよ」「そうですか、こんなもんじゃないですか」「いや、いつもはこんなに食べません。こんなに食べたのは久しぶりだし、最後に一品追加注文されたのは、よほどおいしかったのでしょう」といってくれて、ホッとしました。こんなことを五回くらいやりましたかね、客がだんだんすごい人になっていったと後で聞きました。政財界のいろんな人が見えていたらしいと。
私はそのうちに嫌気がさすんです。冗談じゃない、俺はこんな田舎に料理を作りに来たんじゃない、星岡茶寮に仕事を覚えに来たんだ、これじゃ勉強にならん、と。その時、女中頭が私にさとしてくれるんです。「あなた、やめちゃ絶対にダメですよ。これだけ先生がお客さんをしたことはない。きっと今にいいことがありますよ。それにあなたはまだまだ若いんだから。もう少し辛抱しなさい」
あくる日の朝、東京に連れて帰るからしたくしなさい、と言われましてね、女中頭に、やはりよかったでしょう、と言われました。帰るとすぐ、椀場の主任に抜擢されたのです。(中略)
※岡山県の修業先の娘さんとのロマンスは、親の反対であえなく断念。松浦沖太氏はその後、二一歳の若さで料理長に大抜擢されるとことなる。
自由自在な魯山人の料理の魅力
ふり返って星岡茶寮の何が他の店と違っていたのかを考えてみますと、まず第一に違うのは食器ですね。これは言うまでもなく、魯山人自身が料理を考えながらオリジナルな器を作るわけですから、これは真似のしようのない、最も特徴のある点ですね。
第二は味付けです。化学調味料は一切使いませんでしたし、砂糖もほとんど使いませんでした。素材が新しければそうした調味料を使う必要がないのだ。素材が古く、鮮度が落ちるから調味料を使って補いたくなるのであって、そうでなければ逆効果になって持ち味を殺してしまう。だからこそ材料に鮮度を求めるんだ。これが魯山人の基本的な考え方でした。
第三は料理の演出、変化の演出です。たとえば料理を一人前の皿でひとつひとつ出しますね。それでは、どうしても変化がないからスーッと終わってしまう。そこで魯山人は間に大きな鉢もの、しかも魯山人が自分で焼いた、織部や黄瀬戸などの自慢の器にドーンと盛るんですね。これが実に魯山人らしい効果が出るんです。一方では何でもない素材を何げなく混ぜる。このように眼で見た料理の変化を実にダイナミックに演出するのですね、魯山人は。
さらに、珍味が続くだけでなく、その中に鎌倉で朝獲った菜っぱをさっとゆがいて、揚げ豆腐と炊いて木の芽と出す、といった総菜的な料理を、うんと高価な器に盛ったりするような変化をつけてサマになるのも、魯山人ならではでしたね。魯山人はよく「素材の貧しいものはすばらしい器に盛れ。素材が良ければ、ざんぐりしたものでさっと盛れ」と言ってました。
当意即妙。これも魯山人ならではの極意ですね。雪が降って客ががたがた震えて星岡茶寮に来たとしますね。そうすると魯山人は、献立を無視して、まず熱々の茶碗蒸しをポンと出すんですね。そのおいしさ。心遣いですね、思いやりの心といったらいいでしょうか、細かく客を思いやる。吸い地で作ったおいしい茶碗蒸し。これがちょうど良い蒸し加減の頃合いを見計らってホタテ貝の貝柱を置いて蓋をする。そうすると茶碗蒸しの上にホタテ貝が乗っかって、沈まない。しかも仲居さんが運んでいるうちにホタテ貝に火が入る。これを寒い日に、まず最初に出されたら、客はワーッと温かい気持ちに引き込まれていくわけです。当意即妙、自由自在なんですね。献立は目安であって、生きた料理を、その場で演出していくわけですから、すごいわけです。(中略)
その後、星岡事件というのがあって魯山人が追われ、私もその時に星岡茶寮をやめます。目黒茶寮というのを作ったり、兵隊に行ったり、ハノイで全権大使についていったり戦後も神戸で「魯山」という料理屋をやったりと、語り尽くせないほど様々なことがありました。しかし今考えてみると私にとって魯山人に出会ったということは、何にも代え難い財産だと思います。ここで毎日を送りながら、ここ数年、ようやく昔の星岡茶寮のことを人に語る気持ちになってきたのも、今の時代の人々に魯山人の偉大さを伝えておきたい、と思ったからに他なりません。現代の日本料理にいかに魯山人という天才がたくさんの遺産を残していってくれたことか、そのことを少しでも分かっていただければ、こんな嬉しいことはないと思っています。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)