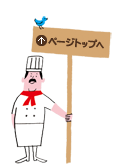変化を恐れず自分の味を追い続けたい

洗練されていながら、ざっくりとした温かみも感じさせる菓子たち。フランス菓子のみならずアメリカ、イギリス……と、各国の影響も垣間見られて、思わずワクワクしてしまう。クラシックなケーキが多い日本のホテル界では異色。それが、パークハイアット東京ペストリーブティックのシェフ、横田秀夫氏がつくる菓子だ。 ※現在は、「菓子工房オークウッド」(埼玉県・春日部)のオーナーシェフ。
「外資系のこのホテルに入り、試行錯誤しながらできたのがいまのスタイル。それまではビシッとした純フランス菓子でした」
と横田氏は言う。アメリカ人の総支配人が「ホームメイドのお菓子が一番いい」というのが印象的だったとか。そういえば、自分でもあっ食べたいなと思うのは、きっちりした緊張感のある美しさより、むしろアットホームな温もりが感じられるもの。これまでの経験にそんな気持ちをミックスして生まれた菓子が、店内に並ぶ。
外観はシンプル。が、食べてみるとアッという驚きがあるのが、横田氏の菓子の真骨頂だろう。(中略)
風味が濃いのに決して重くないのは、素材感を追求した結果の「濃さ」であり、素材の組合せや食感への的確な配慮があるから。
「僕の考える素材の持ち味が、いちばん生きる方法で菓子をつくりたい」
と、横田氏は言う。そして自分の修業時代をこうふり返る。
「いいと思ったことは、変化を恐れず柔軟に変えていこうと思ってやってきました。そうしてできたのが、いまの僕の菓子です」
ホテルと街場のケーキ店、両者を見ることで新しい道へ歩き出す
和菓子店に生まれた横田氏は、父が働く姿を見て自然にものをつくる職業に憧れ、ちょうど洋菓子業界に勢いがあったことからこの業界を志した。高校卒業後、1年制の調理師専門学校に進学。卒業後は街場のケーキ店に勤めようと考えていたが、募集が早かったというひょんなきっかけから1972年にプリンスホテルに就職。ここから横田氏とホテルの菓子との長いつき合いがはじまる。
入ってすぐに横田氏は仕事の厳しさに直面した。当時、洋菓子業界の最先端を行っていたのがホテルだったが、それだけに仕事量は多く、当時は上下関係も厳しく、とにかくハードだった。
「やめたいと思ったこともありますが、こんなに大変な思いをしているんだから、絶対この道で幸せになるぞと思って頑張りました」
ひたすら卵を割る日々が続いた半年間を経て、横田氏は窯、アイスクリーム、仕上げ……と各部門を経験していった。そしてホテル内のフランス料理店に配属になり、横田氏は第一の転機を迎える。洋梨のシャーベットを仕込んでいた時のこと。配合通りに洋梨のピュレ、シロップ、レモンを合わせていたら、「なんで味見をしながら入れないんだ」と、フランス人シェフに聞かれてハッとしたのである。
「それまでは配合通りに、ベルトコンベア式に菓子をつくっていました。生の食材を使う料理人に比べて、加工品を使うことが多い菓子職人はそうした傾向に陥りやすい。彼の言葉がきっかけになって菓子の幅がずいぶん広がりました。確かに味見をして調整しながらつくった方がおいしくできるし、洋梨のシャーベットにしても、ライムを入れたらどうだろうなどと考えながらつくるようになった」
また毎日デザートを手がけるうちに、菓子に対する横田氏の視野はさらに広がった。週替わりで季節のデザートを出すのだが、横田氏は常に新しいものを出そうと意欲的に取り組んだ。シェフになった現在の忙しい身では、素材の新しい組合せに挑戦するにも限度がある。自分を試せる時期に精いっぱいやったこうした蓄積が、いま食感など菓子のバランスを考える時に生かされていると横田氏は言う。
こうして菓子の世界にのめり込んでいった横田氏だが、約5年が過ぎて、同時に仕事の体制への疑問も募っていった。仕事量が多いため、早くこなすことが要求され、自分では完全な仕上がりと思えなくても出さなければならないことがあったのだ。自分でベストと思える菓子を提供したいのに……。ジレンマに陥った横田氏は、いったんホテルから街場のケーキ店に出る。入ったのは、当時、パリの名店「ジャン・ミエ」と提携していた「銀座レカン」。そこで横田氏はショックフリーザーをはじめて知り、急速冷凍させれば菓子の品質を保持しながら生産性も上がることを知る。こうしたシステムの違いや、タルトはよく焼き込んだ方がおいしいなどフランス流のつくり方を学び、横田氏はフランス菓子の技術を煮詰めていった。
が、レカンで1年半ほどすぎたころ、プリンスホテル時代の先輩が今度オープンする全日空ホテルに移ると聞き、横田氏は心を動かされる。街場で学んだことを生かせば、これまでのホテルの菓子とは違うものがつくれるのではないかという思いがあった。ホテルでふたたび自分を試したい。横田氏にとって全日空ホテル行きは、自分がホテルの菓子に感じていた疑問をなくすためのスタートでもあった。
「自分の味」を見つけるため、コンクールに積極的に出て武者修行
そもそも洋菓子が日本に入ってきた当時、外国からの技術者を受け入れる窓口となっていたのがホテル。ホテルが洋菓子業界を引っ張ってきた。が、ホテルは大規模なゆえ流れ作業になりがちな面があり、お客の顔も見えづらい。また、新しいホテルができても系列ホテルの推薦から製菓長が決まるケースが多く、トップが入れ替わることが少ないため、体質を変えにくいという背景があった。一方、街場では、新しい技術を蓄え、お客の動向を見ながら育ってきたケーキ店が勢いづいてきていた。
「街場でできることがホテルでできないはずがない。生意気ながら、ホテルのケーキ事情を少しでも変えたいという使命感がありました」
横田氏は謙虚さは忘れずに、でも前向きに行動した。自分で考えた菓子をシェフに提案したり、そんな菓子が好評を得てレストランのデザートもやらないかと声がかかったりした。またショックフリーザーを取り入れたいと考えていた横田氏は、日本での菓子コンクールに優勝し、ベルギーで開かれる国際大会に出場した際に、機は熟したと考えて行動を起こした。ヨーロッパの菓子事情の報告書を書き、急速冷凍の長所を訴えた。果たして横田氏の実績に注目したトップが報告書に目を通し、ショックフリーザーが設置されることになった。
ところでコンクールといえば、横田氏は修業時代に数々のコンクールに参加している。
「突き詰めて菓子を考える機会は、そうそう自分ではつくれない。自分を最大限に伸ばすためにコンクールにガンガン出ました」
優勝をめざすことによって、他店のケーキもたくさん食べて、どの味がおいしいかを考える。審査員がフランス人の場合、フランス人と日本人が半々の場合など、場面を想定して好まれる味を考える。研究すればそれだけ力量が増して、アレンジやコストについて臨機応変に対応できるようなると、横田氏は言う。そして何よりコンクールは、横田氏にとって「自分の味」を模索する契機になった。
「ジャン・ミエ氏が審査委員長だったコンクールがあったんですが、その時僕は自分で満足のいく味がみつからなくて、ミエ氏のレシピそのままで出品してしまったんです。もちろん落とされました。その時、自分の味を出さなければ意味がないことを思い知った」
「自分の味」のヒントも、横田氏はコンクールをきっかけに見つけた。
「あるコンクールで、キャラメル味のショコラとビスキュイを重ねたケーキをつくり、間にソテーしてキャラメリゼした洋梨を挟みました。その時はそれがベストだと思ったんですが、また試作するうちに、洋梨はソテーするよりも、そのままオー・ド・ヴィ(蒸留酒)をサッとかけて挟むほうがおいしいことに気がついたんです」
ショップで売るにしても、この方が手間がかからず一石二鳥。横田氏はこの一件で思った。手をかけることで味もよくなると短絡的に考えるのは、職人の勘違いにすぎない。シンプルでかつ素材の持ち味を見極めたケーキをつくろう。そこに自分の味を見出そうと。
フランス菓子×アメリカ菓子。これと決めつけるのではなく、お客が喜ぶものを発信する
パークハイアット東京オープンにともなってシェフになったのは94年のことである。客席数180、宴会室4室という高級ホテルながらこぢんまりした規模。しかも外国資本で、多国籍のトップ陣。横田氏はホテルの菓子に、そしてフランス式にやってきた自分の菓子に新たな可能性を見出せるのではと、魅力を感じた。
「これと決めつけるのではなく、お客さまが喜ぶものを発信したい。きっちりしたフランス菓子の『技術』と、ざっくりしたアメリカ菓子の『雰囲気』。一方に固執するのではなく、両者のいい点を生かせれば、時代のニーズに合った菓子ができるのではと思ったんです」
横田氏は、フランス菓子とアメリカ菓子のエッセンスを融合させ、かつ自分らしい菓子をつくることに没頭した。そうして生まれたのが、たとえばデリスショコラ。これはフランスのチョコレート風味の焼き菓子。クラシックショコラを、通常のレシピよりも粉を少なくしてチョコのリッチさを強調したもの。底にはクルミとフランス産のカソナード(赤砂糖)にバター、アメリカ的な食材のグラハムクッキーを混ぜたものを敷き、ザクザクした食感でコントラストをつけた。さらには、ウイーン菓子にホイップクリームが添えられるのをヒントに、ホイップクリームをケーキの表面にトッピングした。
いま店内に並ぶのは、フランス、アメリカの菓子はもとより、中国のデザートにヒントを得たマンゴプリンン、総料理長の故郷、ドイツの菓子がもとになったモーン(ケシの実)トルテなど、横田氏の解釈で新たな息吹を与えられた菓子たち。また、各種デニッシュやマフィン、パン、フランス産バターやイタリアのオリーヴオイルなどの食材まで置かれているのが、特徴的だ。
「このホテルは駅から遠い。それでもお客さまにリピートしていただくためには日常性が高いパンが必要だと思いました。食材も置くのは、自分がすすめられる味をお客さまにも伝えたかったから」
と、横田氏は言う。また、結婚式のケーキは一組ごとのオーダーに合わせてつくるという。街場のケーキ店顔負けのきめ細かな対応だ。職場においては、叱る時はきちんと叱っても、下の者からの疑問に気さくに応えられるような、自然体でカジュアルな雰囲気をつくる。横田氏は、修業時代の経験をもとに次々に自分のスタイルを打ち出した。
「自分に必要なことを取捨選択してきた結果、いまの僕があります。自分を成長させるチャンスにはよく考え、そして柔軟に変われる人間でありたい。パークハイアットは意欲的に挑戦できる職場です」
「自分の味」を追い求めながら、横田氏の菓子は変化し続ける。横田氏の菓子のハッとするおいしさは、そんなひたむきな姿勢の賜である。
■横田秀夫(よこた・ひでお)
1959年、埼玉県生まれ。武蔵野調理師専門学校卒業後、東京プリンスホテル、パティスリー・ド・レカン、東京全日空ホテルを経て、94年のパーク ハイアット東京開業時にペストリーシェフに就任。2004年11月に同ホテルを退職し、同年5月に春日部に「菓子工房オークウッド」を独立開業、3年後の2007年5月には同敷地内に「オークウッド カフェ」をオープン。銀座MIKIMOTO GINZA2内のカフェ「ミキモトラウンジ」のプロデューサーでもある。クープ・デュ・モンド日本代表チーム団長、国際審査委員も歴任。著書に「ホテルのお菓子とデザート」「菓子工房オークウッド 初夏 − 春までの季節感たっぷりレシピ」「菓子工房オークウッド横田秀夫のアイデアデザート」(柴田書店刊)。
URL:http://www.oakwood.co.jp(菓子工房オークウッド)
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)