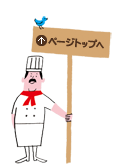暮らし革命の実現こそが外食産業の使命

〝気軽な外食〟の復古が今のところ唯一の到達点 ―外食産業30年の到達地点―
現在日本の食堂業では、直営だけで年商一〇〇億円をあげる企業が七〇社あまり、直営店を一〇〇店以上擁する企業が六〇店あまり出現してきている(1991年当時)。そしてフランチャイズチェーンを含めると約二〇〇社が、一応のビッグストアらしい体裁を整えるようになってきた。食堂業の過去三〇年間の産業化を振り返るとき、これが一番大きな、そして明白な成長の事実である。
しかも、今日そうした規模にまで成長を遂げた企業のほとんどが、スタート時においては確たる基盤を持たない小資本、零細からののし上がり組であるということだ。そういう点では、小売業におけるビッグストアづくりより遅れてはいるけれども、日本の外食業はそれと同じ産業化の道を歩んできている。
そしてその結果として、株式の店頭公開、さらには株式上場を果たす企業も出現した。そのことがとりもなさず、食堂業の産業化三〇年の到達点と言っていいだろう。
しかし逆に言えば、日本の食堂業が三〇年かけてなし得たことは、単にそれだけのことにすぎない。確かに創業者の個人資産が増え、さらにトップは、ビッグストアづくりを成功させた立派な実業家として、社会的にもある程度の認知を受けるまでになったであろう。
しかし企業、とくに生活密着型産業であるところの食堂業においては、その企業としての評価は、〝どれだけ日本人の暮らしを変えたか〟ということを唯一無二の評価基準とするべきである。そうした観点から食堂業を見てみると、すでにできている社会的貢献がひとつある。それは、産業化がはじまる以前にはなかった、より文明的なライフスタイルを人々に提供できたことである。わかりやすく言えば、〝気軽に〟外食ができるようになったということだ。(中略)
ここで歴史をひもといてもらいたい。明治時代、さらには江戸時代にまでさかのぼってみると、主婦や子供も近所のうどん屋やしるこ屋などで〝気軽な外食〟をしていたのである。それが昭和の時代に入って、日本では第一次産業革命が起こり、結果として家庭の稼ぎ手である男性中心の高額外食が主流になっていった。
ということは、現在までにビッグストアづくりを果たした約二〇〇社がなし得たことはこれを取り戻したということなのだ。庶民が外食を、しかも家族構成におけるあらゆる人たちが外食するように〝復古〟したのであって、新しい開拓があったとはまだ言えないのである。しかもこれは、ビッグストアづくりにおいてはひとつの限界である。
だからこそ、食堂業のこれから先の約二〇年は、今までのビッグストアづくりから、本格的なチェーンストア産業づくりに切り換えていく時期だと考える。
胃袋の占拠率に的を絞った経営システムの確立を
なぜチェーンストアなのか。それは「基盤崩壊・構造転換」の時代である一九九〇年代、さらにはその先の時代において、食堂業が本来の使命である〝暮らし革命〟を進めていくためには、それが唯一の道だからである。
現在食堂業はどこでも、深刻な労働生産性の低下と、それによる収益力の伸び悩みに直面している。それらはすべて、基盤崩壊・構造転換、すなわちこれまでの食堂業の産業化を支えてきた基本要素が一八〇度変わってしまったことによるものだ。極言すれば、日本の食堂業は第二の産業化の岐路に立たされていると言ってもいいだろう。
ということは、過去三〇年間に出現した、一応ビッグストアと呼べる体裁を持った約二〇〇社の食堂業も、一〇年後にはその半数近くが姿を消し、さらに二〇年後にはその三分の二以上が消滅してしまうという状況も考えられるのだ。これは新興勢力にとっては絶好のチャンスといえる。
最初に述べたように、これまでのビッグストアづくりでは、スタートはみな零細企業で当時から大きかったところはみな利権企業であるという状況がまずあった。しかしそういう状況だったからこそ、零細企業であっても志があり、的確な方法と手段をとってきたところがビッグストアになり得たのである。
それはすなわち、経営システムとしてその時々の時流に合った〝乗りもの〟に的確に乗り換えたからであったし、それによってそれらの企業は外食を身近なものにし、さらに人々の暮らしを豊かにするための一翼を担ってきた。これは明確な事実であり、かつ食堂業産業化の三〇年で培われた唯一の、しかし最も重要な経験法則である。
しかしこれから先、食堂業がさらに社会に貢献していくために何をすべきかといえば、それはいかに大衆の暮らしを変えられるかということである。それが暮らし革命である。そして暮らし革命には何が必要かといえばそれは絶対的な〝価格の低さ〟なのである。なぜなら常に価格を低くすることでしか、新たなモノの価値は生まれ得ないからだ。
そうした本格的な暮らしの革命を可能にする画期的な経営システムというのは、資金対策、人材組織対策、そしてイノベーション=技術革新対策の三つの柱があって初めて可能になることである。そしてそれこそが、チェーンストア経営システムなのである。現在の日本の食堂業を見る限り、そうした経営システムを確立している企業は一社もないというのが現状なのだ。しかしこの本格的なチェーンストア産業づくりを実現しない限りは、これから先、真の食堂業の産業化は一歩も先に進まないばかりか、逆に家業経営へと逆戻りを余儀なくされるかもしれないのである。
そういう意味では、巷間よく言われるように、食堂業の勢力図が固まってしまったなどというのはどんでもない間違いである。(中略)
食堂業の敵は食堂業ではない。スーパーマーケットやコンビニエンスストアの食品群にこそ真の敵はある。私が一〇年以上も前にこうした主張をした当初は真に受ける食堂経営者はほとんどいなかったが、今やこれを疑うものはいないだろう。ただ、本当にそのことを前提とした経営システムをめざしている企業があるかといえば、まだまだ業界には危機感が薄いというのが私の率直な感想だ。
今までのやり方では、食堂業は確かにオーバーストアだろう。しかし業界としてオーバーストアなのではなく、本来の競争というものがスーパーマーケットやコンビニエンスストアとの、限られた胃袋の占拠率の争奪戦であるという前提に立てば、他の競争相手とはまったく別のカテゴリーでわが社の特徴を打ち出さなければ生き残れないということがわかるだろう。
胃袋の占拠率に的を絞るということは、暮らし密着をめざすことに他ならない。その暮らし密着のフォーマットを実現する唯一の方策が、チェーンストア経営システムの確立なのである。日本の食堂業は今やっと、その経営システムを学ぶためのスタートラインに立ったと言ってもいい。
「高効率の食堂経営を一緒に勉強しよう」
――私が三〇年前、月刊食堂創刊号に寄せたこの呼びかけを、今再びすべての食堂業人に贈ろうと思う。
渥美俊一(あつみしゅんいち)
1926年~2010年。東京大学法学部卒業後、読売新聞社編集局商店経営担当主任記者を経て、67年日本リテイリングセンターを確立する。日本におけるチェーンストア経営指導の第一人者。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)