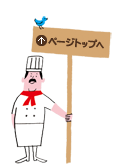菓子職人の喜びとは何か

自分の菓子を表現し続けることこそ、菓子職人の喜び
飛行機は大幅に遅れて深夜のオルリー空港に到着した。1967年6月、河田勝彦氏ははじめてフランスに降り立った。丘の上にある空港からの見晴らしはよく、遠くサクレクール寺院も臨めた。うれしさがこみ上げてきた。なんとかなるよ。不安はなかった。こうして河田氏のお菓子の世界を築く第一歩がはじまった……。
河田氏のお菓子は屹立とした印象が強い。
その特徴は、まず男っぽいこと。シュークリームにしても、タヒチ産バニラがガツンと香るカスタードクリームは、しっかりと火を入れる。アーモンドダイスを散らした生地はギリギリまで火を入れて焼き、カリッと香ばしく風味が高い。メリハリのあるこのお菓子は、その名前もシュー・パリゴー。パリ野郎という意味だ。
そして美しいこと。「フランス人はおいしければいい。形なんか気にしない」と言いながらざっくりとつくるアリ・ババのでき映えは、オレンジピールと生地に浸したシロップがまばゆいほど美しく、表情がある。決めるべきところを決めるから美しいのか。
さらに多彩なこと。コンフイズリー(砂糖菓子)の仕事であるヌガティーヌ(ナッツの飴がけ)やコンフイ(砂糖漬け)などをお菓子に使うことはあたり前。店に一歩入ると、生菓子はもとより、アイスクリーム、伝統菓子、パンやパン菓子、土日にはベニエ(揚げ菓子)も見られる。またヌガーやジャム、キャラメル、フルーツのコンフイが並ぶコンフイズリーはいま河田氏がはまっているアイテム。ショーケースの中でお菓子が楽しそうに並んでいる。さらにちょっとしたそうざい感覚のトレトゥールもある。「パティスリーとはそういうもの」という意識からではなく、お菓子の守備範囲を広げることこそが、新たな自分らしい表現を生み出す原動力だとする考え方があるから、こういう品揃えになったのである。
そんな現在の河田氏だが、この道に入ったとっかかりは単純なものだった。いつも食事をつくってくれたのは、会社勤めの父親だった。そんな環境からか、小さい頃から食べものをつくることは自分にとって自然だったという河田氏は、高校卒業後、東京農業大学栄養科に入学。卒業後は丸の内会館(精養軒)にコックとして就職する。
1964年、折しも東京オリンピック開催の年である。選手村の食事は大手のレストランやホテルの選抜チームが請け負った。選手村の料理長は帝国ホテルの村上信夫シェフ。洗い場しか経験がなく「イモの皮も満足にむけない」河田氏もその中に選出される。彼が受け持つ洗い場の隣は菓子の厨房だった。隣の仕事は、「なにか楽しそう」だった。ひょんなことから河田氏は菓子屋の道へ進むことにした。
当時名が知れた菓子店で、格があると思われた米津風月堂に入る。しかしほどなく同社は倒産するはめになる。他の企業が立て直しに入り、制約が多くなる。経営側とずいぶんとやり合ったという。そんな戦いの末、疲労困憊して2年でそこを去ることになった。
何もかもいやになり、北海道へでも旅に出よう。そう思った河田氏に、フランス行きを勧めたのは兄である。いまから30年以上も前のことで菓子修業にフランスに行く人間はほとんどいなかった時代だが、河田氏は思いを新たにフランス行きの飛行機に乗った。
河田氏22歳の時である。フランスはパリでの生活がはじまった。
労働力に見合うものは賃金。だからこそ労働とは何なのかを意識するべき
2ヵ月分の生活費のはずだった所持金の8万円は、アパートの前払い家賃としてすぐに消えた。1フラン100円の時代だ。ムリもない。とりあえず日本料理店などで働くが、なかなか菓子屋には入れなかった。1967年10月、やっと9区の菓子店「シダ」に入り、3年ものの労働ビザを取得。どうにかフランスで菓子職人としてスタートを切る。が、それもつかの間、翌年春に5月革命に巻き込まれる。
大規模な学生運動を契機に展開されたこの動きは、当時推進されていた経済成長政策のひずみに対する不満をも爆発させ、労働者も巻き込んで拡大した。警察隊との衝突も頻発し、労働者のストライキは各地に広がり、河田氏のいたパリも未曾有の混乱状況に陥っていた。店は閉められ、そして街では投石がくり返された。
「フランスが動かなかった」と河田氏はふり返る。フランスに来てまだ1年足らず。言葉は片言。文化の違い、フランス人の考え方や行動もつかめないでいた。4月には「シダ」を退職していた河田氏は切り詰めて食べていた。社会が揺らぐ中、河田氏の気持ちもまた揺らいでいく。「このまま菓子職人をやっていてよいのか」と。労働とは何かというわけの分からぬテーマが、若き河田氏の心に渦巻いていた。
河田はなけなしの金で1台の自転車を買い、10日間でマルセイユまで走った。その途中、所持金は底をつき、1週間飲まず食わずの日々が続く。野宿で夜をやりすごし、川の水を飲み、道端のリンゴをもいで食べ、教会でパンをもらってどうにか食いつないだ。
「いま思えば、あれは逃げの旅行だったね」
河田氏はポツリとこうもらした。食べるために7月からローヌで住み込みのナシもぎ、モモ狩りの仕事をする。1日25フラン。住み込みなら悪くはない。そして10月にはボルドーに行き、ブドウ狩りの仕事にありついた。菓子のことを頭からすっかり追い払っていた。
「生活のためには働かざるをえない」。それが基本だと体で知った時期である。この時期をふり返って河田氏はこう主張する。「きれいごとで言うんじゃなく、労働とは何なのかを意識するべきだ」と。
「労働力に見合うものは賃金です。菓子職人としてしっかりした思想がなければいい労働もできない。その思想のもと、いい技術でいい菓子をつくれば1000フランのところを1200フランで労働を売れる。雇う側は、その労働の価値を買うわけですから」
思想とは自分の菓子をつくること、その意志表示をすることだと強調する。気持ちを新たにしてボルドーからサンテミリオンに行き、11月にはパリにもどった。途中ボルドーのリブーンという町の「ロペ」という菓子店でカヌレ・ド・ボルドーを見た。そのフォルムと焼き色はいまも印象に残っている。いままで食べたことのない味わいだった。何かやらないといけない。カヌレを見たことをきっかけに「やっぱり菓子職人にならないと」と、「多少自己暗示をかけ、自分を叱咤激励して」気持ちを菓子に向かわせたという。
フランスの菓子は変わらなければダメだと感じていた
それからの河田氏は違った。パリにもどると14区にあるコンフィズリー・ショコラティエ(砂糖菓子とチョコレートの店)「サラバン」をあえて選び、その門を叩いた。この店の砂糖漬けやマロン・グラッセの美しさに惹かれたからだ。チョコレートをカカオ豆からつくっていた店のひとつで、この店の仕事は参考になったという。
1969年6月には5区の「ポンス」というパティスリーに移った。すでに菓子職人としての自意識がはっきり芽生え、河田氏は与えられた仕事を誰よりも早くすませ、給料も上げてもらった。当時、菓子屋ではセクションがはっきり分けられていて、各セクションでは同じ仕事を50年以上も続ける年配の職人が仕事をとり仕切っていた。セクション替えを求めると給料が下げられることから、河田氏は手伝うと称して他のセクションに要領よく入り込み、フォンダンを使うプティ・ガトーやアントルメの補佐、またチョコレートやアイスクリームなど他の仕事も、辞めるまでの1年ほどで覚えていった。
この店を含め、パン屋も入れた合計12店で仕事を覚えていく。そんな中で16区にあったレストラン「ポテル・エ・シャボー」はフランスの国賓関係の宴会などに使われる店で、菓子がうまかった。
「ジェノワーズひとつとっても材料、ルセット(配合、つくり方)が違っていました。技術にもランクがあるんだと知ったのです」
影響を受けた店は他にもある。星つきの「ホテル・ジョルジュ・サンク」では、ベニエやフランベなどクラシックなメニュー、食器使いや演出の仕方が参考になったという。二つ星、三つ星の店には行くべきだと河田氏は言う。ベルギーの「ヴィタメール」では27歳の時、半年間チョコレートの修業をする。当時、フランスのチョコレートは食感が悪くて香りもなく、品質が悪かったからだという。
1973年頃から、後に「ラ・メゾン・ドゥ・ショコラ」を開くロベール・ランクスや、製菓学校を設立するルノートルなどが頭角を現しはじめ、フランスの菓子も変化の兆しをみせていた。
「フランスに行ってすぐの頃からフランスの菓子は変わらなければダメだと感じていた。バタークリームとジェノワーズの菓子が主流で、十年一日のごとく昔ながらの菓子ばかりでおもしろくなかったのです。これではお客に見放されるとずっと思っていましたから」
もっとフレッシュな菓子が出てくるはずと感じていた矢先、シャルロットなどのゼラチンを使ったバヴァロア系菓子などが出はじめた。その日中に食べ切るクリームを使う新鮮な菓子が出てきたのだ。
河田氏は新しい菓子、自分の菓子を求めていたといえる。コンフィズリーやショコラティエの店を意識的に選び、さらに与えられたセクション以外の仕事を積極的に覚えていったのは、そこに理由がある。河田氏は菓子屋の仕事の範囲として、「パティスリー、エピスリー、ショコラティエ、コンフィズリー、ブーランジュリー、トレトゥール、ビスキュイトリー……」と驚くほどの数を挙げる。
「人の菓子をコピーするだけならば本を読めばできる。でもそうじゃない。表現の幅を広げて、自分の菓子をつくろうとするポリシーのあるやつがのびると思う。ランクスやジャン・ポール・エヴァンはもともと菓子職人です。それがチョコレートの仕事を覚えて菓子づくりに幅を与え、自分の表現を加えた新しい菓子をつくった。それが重要だと思う。菓子はトータルな中で追い求めるもの」
と明快に語る。一方、「ポンス」で修業していた頃から河田氏は文献を読みあさるようになった。当時、ある画家と美術館や骨童品などを一緒に見てまわった時に、デザインは時代背景とともにあることを説明される。菓子もまた、文化や歴史を背景に理解する必要があると考えたのである。文献の中で知ったことは新鮮だった。同時に地方へも旅行するようになり、地方菓子へものめり込んでいく。この頃からつくりたい菓子がどんどん浮かんできたという。
1974年、28歳で「ヒルトンホテル・ド・パリ」にシェフ・パティシエとして招聘される。ここで河田氏は、それまで覚えたことを再確認しながら思いの丈自分の菓子を表現していく。充実した1年半がすぎた。
フランスヘ来てから10年ほどの歳月がたった。帰りたいと思ったことは1度もなかったという河田氏だが、やるべきことをすべてやり、帰国を決意した。日本にもどってからは北浦和で5年ほど乾き菓子の卸しをして頭角を現し、そして自分のお菓子を表現する場を求め、1982年に尾山台に店を構えた。開店から数年後、高島屋に出店してからは広く知られるようになり、10年たってお客も定着したという。
河田氏はいま58歳(2001年の取材当時)。そしていまも新しい自分のお菓子を開発し続け、常にショーケースを彩る。そのパワーの源は、自分らしい菓子をつくるのが菓子屋だという、太い根をしっかり張ったポリシーだ。菓子を語る時の河田氏は、目を輝かせて楽しそうである。
![FOODLABO[フード・ラボ]](http://www.ss-foodlabo.com/img/interface/logo.png)